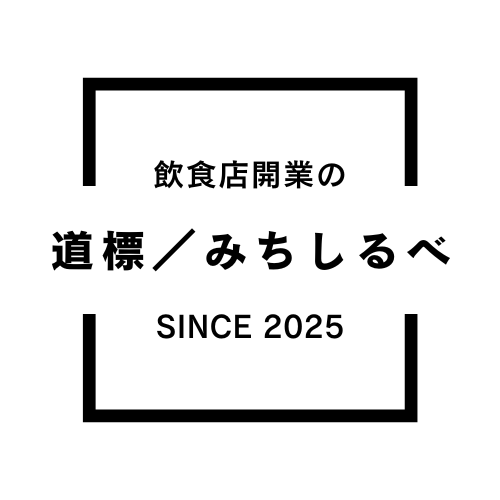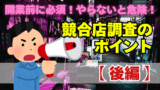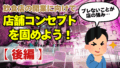自分のお店(自店)を開業する際、数多くのお店がある中から顧客に選ばれ、来店してもらう根拠(来店動機)の一つとなるのが周辺環境や近い将来、競合店となるお店の存在です。
一昔前であれば「新しくオープンしたお店があるから一度行ってみようか?」と足を運んでもらえたかもしれませんが、InstagramやX(旧Twitter)といったSNSなどで飲食店の情報を簡単に入手できるようになった現代では、顧客から「他店とは違う魅力があるお店」と認識されなければ来店してもらうことが難しくなってきています。そのためには、競合店調査が欠かせません。
本記事では、前編・後編に分けて飲食店開業に欠かせない競合店調査の考え方、ポイント、活用方法などを詳しく解説しますので是非最後までお読みください。
この記事は以下のような人におすすめ!
- 飲食店開業に向けて準備・検討している方
- 飲食店開業に向けて競合店の情報を収集したい方
- 飲食店開業に向けて競合店との差別化を模索している方
競合店調査が必要な理由とは?
開業の準備を進めるにあたり、「料理さえ美味しければ、集客できるだろうから競合店のことを意識しなくても良いだろう」と考えるのは非常に危険です。仮にその後、お店が繁盛したとしてもそれは結果論にすぎません。
事前に出店エリアの周辺状況、競合店の情報、顧客動向などを把握しておくことは、客観的な視点で自店の強みと弱みを明確し、競合店との差別化を打ち出すために必要不可欠です。今、市場・顧客に求められているものが何なのかを明らかにするためにも目的をもって競合店の調査に取り組みましょう。
一言で競合店調査といっても専門性の高いものから基礎的なものまで様々です。より徹底した調査を行うに越したことはありませんが、専門性の高い調査には相応の知識、時間、労力が必要です。大切なのは限られた時間の中で効率的に役立つリアルなデータを集めることです。本記事の後編では気軽に取り組める基礎的な調査についてご紹介していきます。
競合店調査の前提になること
調査に取り組むうえで注意しなければならないのは出店を検討しているエリアに一定のニーズが見込めなければ調査を行っても意味がないということです。
つまり、このエリアには競合店が存在しない穴場だから、出店すれば集客できるだろうと安易に考えるのは非常に危険だということです。競合店が存在しないにはそれなりの理由があると考えるのが妥当と言えるでしょう。
そのため、本当にそのエリアに一定のニーズが存在しているかを判断するには競合店が存在していることが重要なポイントになります。リスクはあるものの穴場と思われるエリアに出店するか、競合が多く、家賃も高いがニーズが確実に存在するエリアに出店するかは明暗を分ける大きな決断となるため慎重に判断する必要があります。
競合店調査に関して興味深いデータがあります。ファーストフードチェーンの最大手であるマクドナルドは新店舗の出店時におけるマーケティング調査の精度が極めて高く、売上予測が5%の範囲内に収まると言われています。マクドナルドに尋常ではない調査力があることは確かですが、売上予測が担当者の「勘」だけではなく、綿密な分析によって導き出された調査結果として重要性を示すものと言えるでしょう。
商圏人口・駅乗降者数・店前通行量の把握
競合店調査を行う前に把握しておくべきポイントとして、商圏人口(お店を展開する時に来店が見込める範囲に居住する人口)、駅乗降者数、店前通行量があります。売上を予測するうえでの重要な指標となるため、必ず把握しておきましょう。
商圏人口
飲食店の基本的な商圏(ビジネスを展開する時に来店が見込める地理的な範囲のこと)は、大きく分けて以下の2パターンと考えましょう。
- 郊外・住宅街の場合はお店から半径3km(地方の場合は5~7km)
- 繁華街・駅前の場合はお店から半径1km(都心部の場合は500m)
まず出店を検討しているエリアの商圏内に何人が居住しているかを調べましょう。
地域の行政機関(区役所や市役所など)では、定期的に自治会ごとの世帯数・人口の統計をとっており、その多くがインターネット上で公開されています。地域によっては自治会ごとの人口・性別・年齢層までが公開されています。
駅乗降者数
出店を検討しているエリアが繁華街・駅前の場合は鉄道の最寄り駅(エリアによっては複数)からの距離、乗降者数、店前通行量も調べましょう。駅の乗降者数の情報は以下のウェブサイトなどで調べることができます。
- オープンポータル(国土数値情報ダウンロードサービスの情報を元にしたデータです。)
- ウィキペディア(Wikipedia)で〇〇駅と検索すれば大半の駅における1日の平均乗車人員を確認できます。
店前通行量
店前通行量とは、お店の前を通る歩行者の人数のことです。当然のことですが店舗の入り口前の歩行者数が多ければ多いほど、店に立ち寄る人数(来店客数)は増え、結果として売上に結びつく可能性は高くなります。
厳密なデータをとるには労力がかかる大変な作業ですが、平日、土日などに分けて時間帯ごとの店前通行量を把握しておくことは「そこにたまたまそのお店があったから」という理由で来店する「機会来店」を見込むうえで、看板などのお店の外観の作り込みに影響するため重要となります。
- 最近ではスマートフォンの人流データから店前通行量を調べるサービスもありますが、調査費用が高額なため、小規模なお店の開業には不向きです。
- データや地図による情報収集も重要ですが、実際にエリア周辺を歩いて地域の特性を肌で感じることも欠かせません。駅周辺のエリアでも通りを一つ跨げばガラッと人通りが減り、別世界になるということもよくあります。実際に人の流れ、街並みなどを目で見ることでデータ上では分からなかった地域特有の個性やニーズを把握できるため是非実践してください。
競合店調査を行うタイミングは?
調査は開業準備の早い段階から出店エリアをある程度想定して取り掛かり、その内容を店舗コンセプトに反映させましょう。まだどんなお店にするか具体的にイメージできていない場合は、競合店の優れた点を参考にすると良いでしょう。
まとめ
今回は競合店調査が必要な理由やポイントなどについてお伝えしました。
競合店の調査を行うことはお店のコンセプトを固め、競合店との差別化をはかるうえで欠かせません。開業を成功に導くために自身の感覚に頼るだけではなく、広い視野で調査に取り組みましょう。
後編では競合店調査を行う際のポイントや調査結果の活用方法について詳しくお伝えしますので是非続けてお読みください。