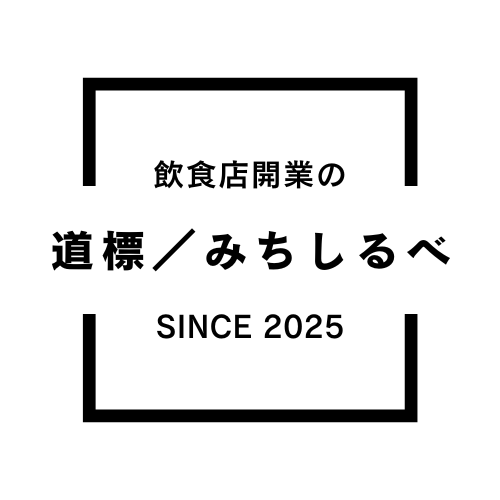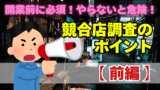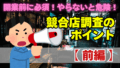前編では、競合店調査が必要な理由と競合店調査を行う際の前提などについてお伝えしました。後編では、競合店調査を実施する際のポイントや調査結果の活用方法について詳しく解説していきますので是非最後までお読みください。
この記事は以下のような人におすすめ!
- 飲食店開業に向けて準備・検討している方
- 飲食店開業に向けて競合店の情報を収集したい方
- 飲食店開業に向けて競合店との差別化を模索している方
競合店調査のポイント
近年ではネット上の食べログやぐるなびのグルメサイトなどで飲食店の情報を収集することが可能ですが、その情報だけに頼るのではなく実際に出店を検討しているエリアの繁盛店・競合店でサービスの提供を受け、そのお店がなぜ繁盛しているのかを身をもって調査し、自店の強みや弱みを可視化することが大切です。
調査対象
出店するエリアが繁華街や駅前であれば競合店は相当な数になるため、対象となる店舗を絞り込むだけでも大変です。その場合は自店と似たコンセプト(ターゲット層、料理、業態など)のお店を優先的に調査しましょう。また、商圏が異なるお店でもコンセプトが近く、繁盛しているお店には足を運んで、なぜ繁盛しているのかを探っておきたいところです。
チェックシートの準備
調査は「美味しかった」「サービスが良かった」という感想をまとめるだけでは意味がありません。事前に確認したい項目を列挙したチェックシートを準備しましょう。ここでは、基本的な確認項目を紹介しますが、他にも注目しておきたいポイントがあれば項目を追加しましょう。
競合店調査確認項目(参考)
| 基本情報 | ・店舗名 ・営業時間 ・定休日 ・自店からの距離 |
| 立地・外観 | ・店前の人通りは多いか? ・入口はわかりやすいか? ・ネット上に地図情報は公開されているか? ・駐車場は何台あるか?(郊外立地の場合) ・看板の位置や視認性は? ・一目でどんなジャンルのお店か分かるか? |
| 内観 | ・外観の印象と一貫性があるか? ・店内の雰囲気は? ・照明の明るさは妥当か? ・テーブル、イスの品質は?使いやすいか? ・清掃が行き届いているか? ・お手洗いは清潔で使いやすいか? |
| 客層 | ・来店客の年齢層は?性別は? |
| 席数 | ・カウンター、テーブル、座敷の席数は? ・個室は何室あるか? |
| 料理・メニュー | ・メイン料理の内容は? ・料理に独創性はあるか? ・食材は新鮮か? ・味付けは? ・料理の温かさは適切か? ・ボリュームは価格に見合っているか? ・おすすめや季節メニューはあるか? ・メニュー表はどんなデザインか? |
| 価格 | ・想定される客単価は? ・メイン料理の価格帯は? ・ドリンクの価格帯は? |
| 接客・サービス | ・座席案内やメニュー案内は適切か? ・従業員の身だしなみ、言葉遣いは? ・従業員は笑顔で接客しているか? ・料理提供時間は適切か? |
| 販売促進 | ・販促用のPOPは掲示してあるか? ・BGMはお店の雰囲気に合っているか? ・スタンプカードやクーポンはあるか? |
注意点
- 調査日時、曜日は忘れずに記録しておきましょう。平日と休日、来店時間帯によって客層が変わることも考慮する必要があります。
- あからさまに調査していることがわかるような行動はお店側へ不信感を与えるため避けましょう。重要なポイントだけをスマートフォンのメモ機能に残すようにするなどの配慮も必要です。また、写真や動画を撮る際には事前にお店側の許可を得ることが鉄則です。
- 飲食業界での経験が豊富な方ほどお店の悪いところに目が行く傾向にあります。調査の目的は悪いところの粗探しだけではなく、良いところを探すことです。
これらの項目をチェックしていけば、調査したお店の「実態」が見えてくるだけでなく、同時に開業に向けて自店の課題も見えてくる筈です。実績のあるお店の「顧客の来店動機」と「その店の強み」をしっかりと把握することが大切です。
競合店調査に活用できるフレームワーク(参考)
フレームワークとは目標達成や経営戦略、課題解決に役立つ思考の「枠組み」「骨組み」を意味する言葉です。フレームワークを活用すれば、競合店調査の結果を活かして、店づくりを効率的に行えます。フレームワークにはさまざまな種類があるため、目的に合ったものを選びましょう。ここでは、競合店調査に活用できるフレームワークとして代表的な「SWOT分析」を簡単にご紹介します。
SWOT(スウォット)分析
SWOT分析とは、「強み(Strength)」、「弱み(Weakness)」、「機会(Opportunity)」、「脅威(Threat)」の頭文字を取った分析手法で、主に既存の事業者が現在の内外の環境を見直して、新たな戦略を構築するときに用いるものですが、開業の際も事業の成功イメージを作ることに活用できます。
SWOT分析では、競合店と比較した場合の相対的な内部環境を「強み」と「弱み」、自店を取り巻く外部環境を「機会」と「脅威」をカテゴリーに分けて以下のような考え方で一覧にします。
SWOT分析の表(表内は考え方)
| 内部環境 | ●強み 自店(自分)の強みを列挙します。 競合店にはない差別化できる特徴を具体的にあげましょう。 |
●弱み 自店(自分)の弱みを列挙します。 競合店と比較して足りていないことや苦手とすることをあげましょう。 |
| 外部環境 | ●機会 市場変化などにより自店のプラス(チャンス)となりうる要素を列挙します。 小さな社会の動きでもチャンスにつながる要因はあげましょう。 |
●脅威 市場変化などにより自店にマイナスに働く要素を列挙します。 小さな変化にも着目し、将来的なリスクとして捉えましょう。 |
SWOT分析では比較的列挙しやすい自店のプラス要素だけではなく、目を逸らしがちなマイナス要素もあげていくことが求められます。リスク管理の観点からも後々不安材料となるマイナス要素をしっかりとさらけ出していきましょう。以下は繁華街で開業する居酒屋をモデルとした具体例です。
具体例…居酒屋
| 内部環境 | ●強み
|
●弱み
|
| 外部環境 | ●機会
|
●脅威
|
SWOT分析は、ただ4つのカテゴリーを埋めるだけの作業ではありません。列挙した内容を活かして戦略を立てることがSWOT分析の有効な活用方法です。以下のように内部環境と外部環境を掛け合わせて自店の戦略を考えていきましょう。
①強み×機会
→自店の強みを活かし機会を最大限に活用する戦略
②強み×脅威
→自店の強みを活かし脅威を切り抜けるための戦略
③弱み×機会
→自店の弱みによって機会を逃さないための戦略(弱みの克服)
④弱み×脅威
→自店の弱みと脅威による最悪の事態を回避する戦略
この中でも特に重要なのは①の強み×機会の戦略です。強みを活かしながら機会を最大限に活用し、市場の拡大や売り上げに繋げることはビジネスの中でも最も優先される戦略と言われています。
また、③の弱み×機会における自分の弱みの克服することは重要な課題です。開業前の時間が確保できる時から取り組まなければチャンスとなる機会を活かすことができません。
調査結果をどのように活用するのか?
競合店調査から得られた情報は、その内容をしっかり振り返り、以下のポイントを店舗コンセプトへ反映させていきましょう。
良いところは徹底的に学び、吸収する
繁盛店には、必ず成功している理由が存在します。「なぜこのお店は顧客から支持されているのか?」という観点からその理由を推測しましょう。その中から自店でも取り入れたいこと、より良いものへ発展させたいことをピックアップし、店舗コンセプトへ組み込んでいきましょう。競合店の良いところは徹底的に学び、吸収するという姿勢が大切です。
ここで注意していただきたいのは、いわゆる「パクリ」です。明らかに競合店のモノマネと受け取られるメニューやサービスを提供することは顧客から違和感を抱かれることもあります。また、競合店から見ても気持ちの良いものではなく、トラブルに発展する恐れもあります。競合店を参考にしたメニューやサービスは自店のオリジナルと言い切れるものになるまで磨きあげていきましょう。
競合店の弱みを差別化に活かす
競合店に弱みが見つかった場合、その弱みをチャンスとして捉えることが大切です。自店ではそこを磨き、強みとすることで差別化のポイントとして打ち出しましょう。
ターゲットの変更も検討する
競合店調査の結果次第ではターゲットとなる客層を変更するのもひとつの考え方です。競合店と同じ商圏で同じ客層を狙うのが難しいと思われる場合は、提供するメニューやサービスなどのソフト面だけではなく、内外装やレイアウトの変更などのハード面の見直しも視野に入れて店舗コンセプトを練り直しましょう。
競合店調査は、定期的に行うことが大切です。飲食業界の顧客ニーズやトレンドは常に変化し続けています。一度調査したからといって終わりではありません。開業後も気になる競合店には定期的に足を運び、情報収集することを習慣にしていきましょう。
まとめ
今回は前編・後編にわたって競合店調査についてお伝えしました。競合店調査はただやみくもにやれば良いわけではありません。目的をもって競合店を調査し、その結果を店づくりに反映させることがなにより大切です。
飲食業界における経験値はプラス要素でもありますが、その分、先入観にとらわれてしまい、視野が狭くなりがちです。今一度、顧客目線で競合店を調査し、良いところは大いに学び、自店の強みを磨くことで競合店との差別化を明確に打ち出しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。