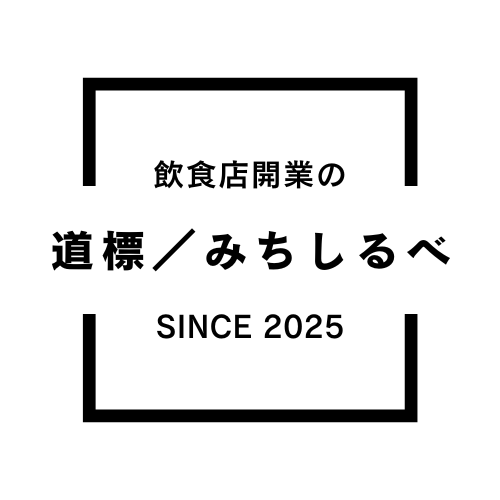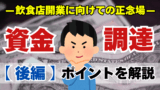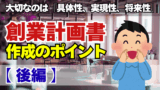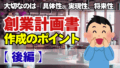店舗コンセプトが固まったら、次のステップとして創業計画書を作成しましょう。
創業計画書は生存競争の激しい飲食業界において、自店がどのようにポジションを確立し、生き残っていくのかを具体的に示す重要なアイテムであり、金融機関から融資を受けようとする際には必ず作成しなければならないものです。
飲食業界での経験が豊富でも、創業計画書を初めて見聞きする方も少なくないでしょう。自店が成功するために何が必要であるかを考えながらじっくり作り上げていきましょう。
本記事では、前編・後編に分けて創業計画書を作成するうえでのポイントについて詳しく解説しますので是非最後までお読みください。
この記事は以下のような人におすすめ!
- 飲食店開業に向けて準備・検討している方
- 創業計画書を初めて見聞きする方
- 開業にあたり融資を受けようとしている方
創業計画書とは?
創業計画書とは、開業にあたっての事業内容、資金計画、収支計画などを具体的にまとめた書類のことです。必ず作成しなければならないというルールはありませんが、開業の際に金融機関からの融資を申し込む際には提出することが必須となります。その内容は融資の審査における重要な判断材料となるため、計画の具体性、実現性、将来性が求められます。
なぜ創業計画書が必要なのか?
創業計画書は融資を受けるためだけに作成するものではありません。たとえ開業費用が少額で、融資が必要ないケースであっても作成することをおすすめします。その理由は以下の通りです。
事業内容を具体的にするため
創業計画書を作成することによって、漠然とした目標を具体的な文章や数値に落とし込むことができます。それにより自身の事業に対する理解を深めることができ、将来に向けたビジョンも明確になります。
必要な資金や収支目標を明確にするため
創業計画書には、開業するために必要な物件取得費や設備費などの設備資金と、店舗運営にかかる運転資金をどのように調達するかをまとめた「資金計画」と開業後の売上、経費、利益などの見込みをまとめた「収支計画」が含まれます。それらの数値を固めることで計画の具体性が増し、目指すべき目標が明確になります。
融資を受けるため
繰り返しになりますが金融機関からの融資を受ける際には創業計画書の提出が求められます。新規開業は事業の実績がないため、創業計画書の内容により融資の可否が決まると言っても過言ではありません。そのため、金融機関から見て、事業の将来性や返済の見通しを明確に示す内容になっていることが求められます。
創業計画書はいつ作る?
出店エリアを想定し、店舗コンセプト作りと競合店調査を並行して行った後に創業計画書を作成することをおすすめします。そうすることで出店のイメージを明確にすることができ、その後の物件選びや融資の申し込み手続きがスムーズに進むようになります。最初に物件を決めてしまうと、全てが後付けになり、難易度が高くなるため注意が必要です。
作成にあたってのポイント
創業計画書を作成するうえで理解しておくべきポイントは以下の通りです。
自分自身で作ることに意味がある
創業計画書の作成をコンサルタント会社や税理士などに費用を払って依頼する方法もありますが、あまりおすすめできません。融資の審査では金融機関の融資担当者との面談があり、計画書の内容について質問されます。その際に自分が作成したものでなければ、うまく受け答えできないこともあり、悪い印象を与えかねないからです。計画書を作成する過程での学びも多いため自分自身で悪戦苦闘し、作り上げた方がプラスになるでしょう。
統一の様式はない
創業計画書には統一の様式はありません。金融機関ごとの定められた様式に沿って作成することが一般的です。そのため、金融機関によっては様式が異なれば作り替えなければならないこともあります。
追加資料はプラス材料
様式に収まり切らない内容は追加資料として創業計画書につけ加えることができます。提供する料理の写真、競合店調査の一覧表、収支計画の詳細など創業計画書の説得力が増すような資料は審査においてプラス要素になります。必要に応じて作成し、提出しましょう。
ITスキルは必須
創業計画書は手書きでも作成することもできますが、パソコンを使って作成することをおすすめします。
今やITなくして飲食店経営は成り立たないと言っても過言ではありません。開業後はPOSレジをはじめ、SNSによる集客、キャッシュレス決済、会計業務など、様々なシーンでIT技術を活用していくことが求められます。パソコンの操作に不慣れな方は開業の準備を通じてITスキルを高めていきましょう。
まとめ
今回は創業計画書の作成のポイントなどについてお伝えしました。
創業計画書を作成することで漠然としていた目標を具体的な言葉や数値に落とし込むことができます。自身の事業への理解を一層深め、将来のビジョンを明確にするうえでも欠かせないツールとなるため、焦らず時間をかけてじっくり作り上げていきましょう。
後編では創業計画書の書き方について詳しくお伝えしますので是非続けてお読みください。