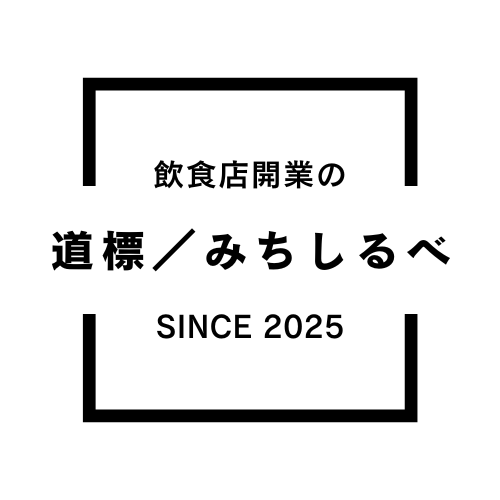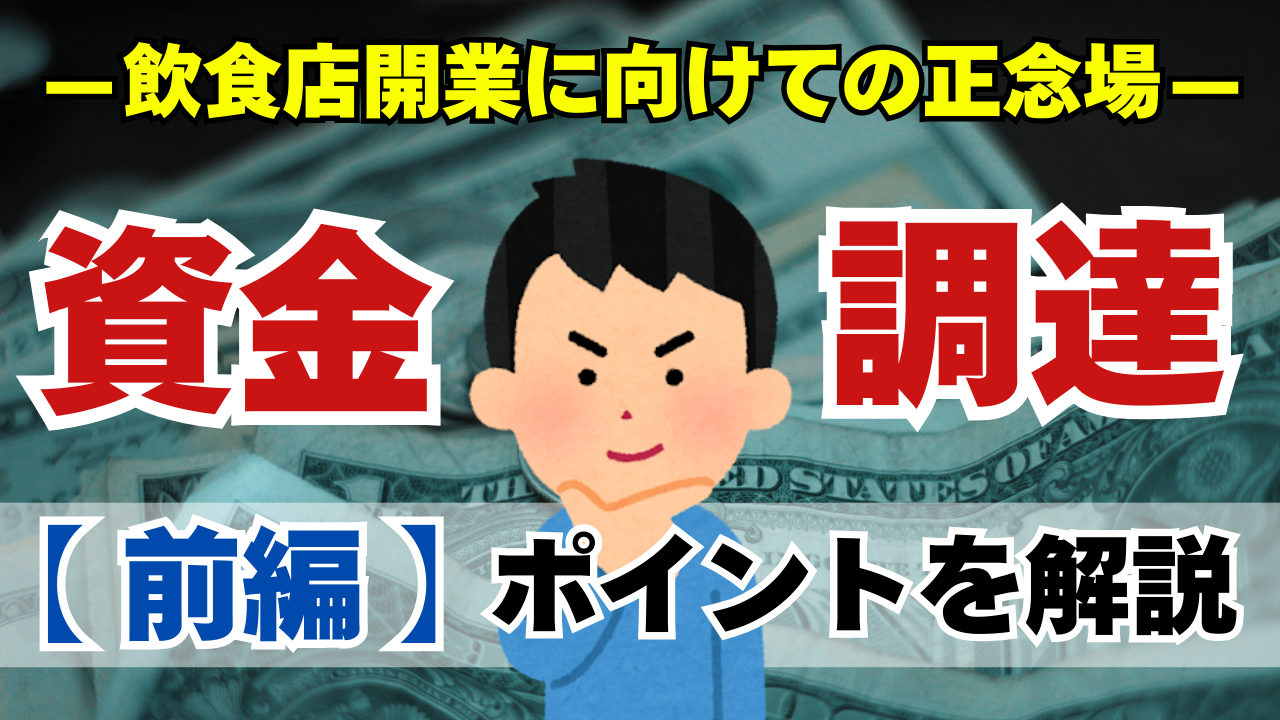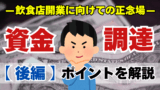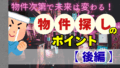創業計画書が完成し、物件が決まれば、次はいよいよ資金調達です。
開業時の資金調達では金融機関から融資を受けることが一般的です。そして金融機関から融資の結果によって開業できるかが決まると言っても過言ではないため開業に向けた正念場とも言えるでしょう。
住宅ローンやカーローンなどで借入の経験があるものの、事業資金の融資を申し込むのは初めてという方が多いでしょう。最も大きな違いは、創業計画書に記入した事業内容に基づき審査が行われるという点です。そのため、準備する創業計画書には事業の具体性、実現性、将来性が求められる他、その内容に関する質問に対して、面談でしっかり受け答えができるようにしておく必要があります。準備を整えて融資を申し込みましょう。本記事では、前編・後編に分けて飲食店の開業における資金調達のポイントについて詳しく解説しますので是非最後までお読みください。
この記事は以下のような人におすすめ!
- 飲食店開業に向けて準備・検討している方
- これから融資を受けようとしている方
- 融資について詳しく知りたい方
どのような資金調達方法があるのか?
開業資金の調達方法には自己資金でまかなうこと以外に、外部から資金を集める方法があります。外部から資金を集める方法は、主に以下の3つです。
金融機関からの融資で調達する
開業にあたって融資を受ける場合、日本政策金融公庫(以下、日本公庫)へ申し込むか、民間の銀行経由で各自治体が窓口となる制度融資を利用することが一般的です。この記事では、多くの飲食店が利用している日本公庫の融資について解説します。
日本公庫とは、国が100%出資する中小企業・小規模事業者などの創業や創業後の経営を支援する目的で設立された政府系金融機関です。年間110万社を超える融資実績があり、個人事業主として飲食店を開業する方も多く利用されています。
日本公庫の「新規開業資金」は、原則として無担保無保証人で借り入れができる融資制度です。
融資で借りられるお金は、飲食企業へ一定期間勤務した経歴(少なくとも3~5年以上)がある場合で、自己資金の3倍程度が目安になります。
ただし、自己資金が500万円あったとしても、その3倍にあたる1,500万円の融資が受けられるとは限りません。いくら好条件が揃っていても新規開業は事業実績がないため、金融機関は本当に返済してもらえるのか慎重に判断します。個人で開業する際の借入金の上限額は1,000万円程度と考えていた方が妥当でしょう。
補助金や助成金を利用して調達する
国や地方自治体などから支給される補助金や助成金を利用して、開業資金の一部を調達する方法もあります。補助金は採択件数や金額に限りがあるのに対し、助成金は要件を満たせば誰でも受給できるものであることが特徴です。補助金や助成金を利用するうえでのメリット・デメリットは以下の通りです。(市区町村における補助金、助成金の制度や要件は地域によって異なります。開業する地域の地方自治体のホームページなどでご確認ください。)
〇補助金や助成金を利用するメリット
補助金や助成金は借入金ではないため、原則として返済は不要です。開業後はすぐに利益が出せるとは限らないため、返済の負担がないことは資金繰りの助けになるでしょう。
〇補助金や助成金を利用するデメリット
- 補助金や助成金にはそれぞれ目的や対象となるための条件が細かく定められています。条件に合わなければ申請することはできません。
- 補助金や助成金を申請するためには多くの書類を作成しなければならないため、開業前後の忙しい時期には大きな負担になります。また、たとえ受給できることになったとしても、事務処理や事後報告などにも手間がかかります。
- 補助金・助成金は前払いではありません。原則として後日精算する流れになるため、立て替える資金は融資などで調達する必要があります。
親族・知人などからの借入で調達する
親子間での借入が一般的です。金額が大きいと贈与とみなされかねないため、たとえ親子間でも借用証書を取り交わすようにしましょう。
金融機関からの借入とは異なり、交渉次第では返済期間も比較的柔軟に対応してもらえるでしょう。ただし、返済が滞るなどした場合は相手との関係性が悪くなることもあるため慎重に判断しましょう。
融資を断られる原因になりうるものとは?
日本公庫は申込者の返済能力を調査することを目的として、個人の信用情報を確認しています。そのため、以下に該当する方は創業計画書の内容に問題がなくても融資を断られるケースがあります。
- 税金の未納、滞納がある。
- 消費者金融からの借入が多い。
- 過去のローンやクレジットカードなどの支払いが滞っており、信用情報に問題がある。
資金使途とは?
開業時の融資における資金使途(資金の使い道)は物件取得費、内外装工事費、設備導入費などの「設備資金」が一般的です。「設備資金」は仕入れ、家賃、人件費などの「運転資金」に比べ、返済期間を長期で組むことができ、月々の返済額を抑えられるメリットがあります。
なお、日本公庫の新規開業資金の返済期間は最長で設備資金20年以内(うち据置期間5年以内)、運転資金10年以内(うち据置期間5年以内)となっています。(返済期間について日本公庫へ問い合わせてみたところ、設備資金で返済期間が20年となるケースは、大規模な設備投資をした場合に限られるため、創業時の融資(設備資金)における返済期間は、10年以内となることが多いようです。)
据置期間とは、借入した元本の返済が猶予され、利息だけを支払えば良い期間のことです。借入後、すぐに返済を開始することもできますが、お店が軌道に乗るまで半年程度の据置期間を設けることが一般的です。
融資を受けるまでの流れ
日本公庫で融資を受ける際の流れは以下の通りです。
融資の申し込みや事前相談は、日本公庫の各支店や各地の商工会議所、商工会などで受け付けています。また、窓口を訪れる際には事前に電話で予約するようにしましょう。
①インターネット申し込み(推奨)
日本公庫公式サイトのインターネット申込のページから手続きを行いましょう。申込の際には以下の書類を電子データで添付するようになります。
- 創業計画書
- 見積書(物件取得費、内外装工事費、厨房機器購入費など10万円以上で取得予定のもの)
- 履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合)
- 運転免許証またはパスポート
- 飲食店営業に関する許認可証(後日の提出でも可)
郵送や持参による申し込みの場合
- 上記の書類以外に「借入申込書(国民生活事業用)」が必要になります。借入申込書(国民生活事業用)は日本公庫公式サイトの各種書式ダウンロードのページからダウンロードできる他、日本公庫の各支店や各地の商工会議所、商工会などの窓口で配布されています。
- 提出した書類は返却されませんので原本ではなく、必ずコピーしたものを提出しましょう。
②書面審査
③面談(後編参照)
④審査
⑤審査結果の連絡
⑥契約手続き(借用証書の提出など)
⑦融資金入金(指定した口座への振り込み)
⑧返済開始
融資決定までにかかる期間
開業にあたっての融資の審査には時間がかかります。申し込みから結果が出るまでに1ヵ月程度かかると考えておきましょう。
提出書類の不備などがあった場合には、さらに審査や入金が長引くこともあります。物件の本契約や内外装工事の発注などのスケジュールは余裕をもって組みましょう。
まとめ
この記事では、資金調達のポイントについてお伝えしました。
飲食店の開業には平均で1,000万円程度の資金が必要と言われており、新規開業者の多くは金融機関から融資を利用しています。融資の決め手となるポイントをしっかり押さえて必要な資金の調達を目指しましょう。
後編では融資を申し込む際の面談のポイントや融資における疑問点について詳しくお伝えしますので是非続けてお読みください。