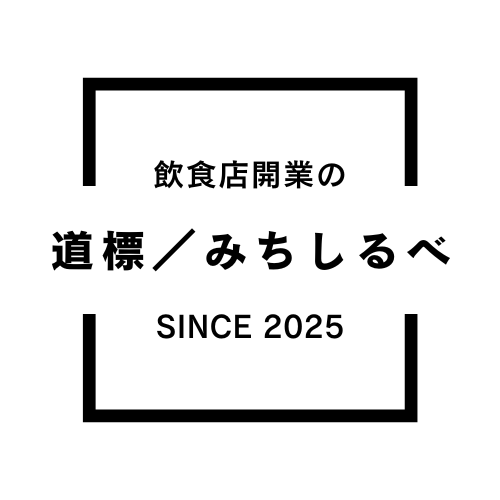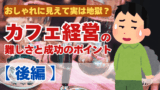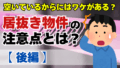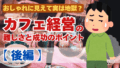今回は私がこれまで受けてきた開業の相談の中で最も多かった業態「カフェ」についてお伝えしていきたいと思います。
結論から言うと余程の覚悟がなければカフェの経営には手を出さない方がいいです。それは私の経験上、失敗のリスクが最も高い飲食業態がカフェだと考えているからです。
私が住む地域(人口約20万人)でも毎年のように新しいカフェがオープンしています。しかし、スターバックスやドトールコーヒー、コメダ珈琲などの大手カフェチェーン店を除けば、大半がオープンから早々に閉店しており、私が把握している限りでは近年、新規開業した個人経営のカフェで5年以上続いているカフェはごくわずかです。閉店率は8割以上でしょう。
これからカフェをやってみたいと考えている方には耳の痛い話になるかもしれませんが、なぜカフェの経営は難しいのか?をしっかり理解したうえで、それでも敢えてカフェ業態に挑戦するのかを判断してください。
本記事では、前編・後編に分けてカフェ経営の難しさと成功のポイントついて詳しく解説していきますので是非最後までお読みください。
この記事は以下のような人におすすめ!
- 飲食店開業に向けて準備・検討している方
- カフェ業態での開業を検討している方
- カフェ経営を夢見ている方
カフェをやりたいという人の傾向
これは私がこれまでに相談を受けてきたカフェをオープンしたいという方の傾向ですが、「儲からなくてもいいから細々とやっていきたい」というスタンスの方が圧倒的に多いです。そして実際に開業する方の比率も低い…つまり他の飲食業態と比べて開業の動機が軽い方が多いということです。逆にカフェ業態で儲けることに目をギラつかせている方にはほとんど会ったことがありません。
開業資金はそれほどないから低コストでオープンしたい、だから、お店の作りに尖ったものがなく、中途半端な店構えになってしまう…そこまでコーヒーに関する知識や焙煎の技術、特別な料理が作れるスキルはない、だから、どこにでもあるような無難なメニューしか提供できない…その結果としてこれといった特徴のないお店になってしまう…大半がこのパターンに該当します。ただでさえ利益を上げることが難しいとされるカフェ業態において、これでは勝ち目はありません…
多様化するカフェ業態
大手カフェチェーン店では、カウンターでオーダーして飲物を受け取り、自身でテーブルまで運ぶセルフスタイルが定着しており、現在のカフェ業界で大きなシェアを持っています。
その一方、小規模のカフェではコンセプトが多様化してきています。競争の激しさは増しているものの、魅力あるコンセプトとメニュー、SNSによる情報発信次第では人気店になりうる可能性も示されています。また、近年ではフードメニューの充実を図るカフェも増加しており、レストランやファストフード店との違いもあいまいになってきています。
カフェと喫茶店の違い(参考)
以前、カフェと喫茶店は営業許可の種類によって区別されていました。喫茶店営業許可ではアルコール類の提供、調理を必要とする料理の提供はできませんでしたが、2021年の法改正で喫茶店営業許可が廃止となり、喫茶店もカフェと同様の飲食店営業許可に統合されたため、法律上のカフェと喫茶店の違いはなくなりました。現在は両者に明確な違いはなく、店舗のイメージやコンセプトに合わせて自由にカフェや喫茶店を名乗ることが可能となっています。
カフェ経営は儲かるのか?
「カフェ経営は儲かるのか?」と聞かれたら、私は「普通にやっても儲からない」と答えます。これまで出会ってきた複数のカフェ経営者にも実際に儲かるのかを聞いたこともありますが、一様に「儲からない」という答えが返ってきました。
なぜならカフェという業態は「低単価滞在型(客単価が低く滞在時間が長い)」だからです。これがカフェ経営の難しさの根本的な理由と言えるでしょう。
カフェの経営が難しい理由とは?
飲食店の中でもカフェ業態の経営が難しいとされる具体的な理由は以下の通りです。
客単価の低さ
カフェ経営の難しさの最も大きな理由は客単価の低さです。カフェの主力メニューはコーヒーをはじめとするドリンクです。コーヒーにおいてはどれだけ焙煎の技術が高く、希少な豆を使っていたとしても極端に高い価格を設定することはできません。また、たとえ魅力的なドリンクメニューを豊富に取り揃えたとしてもアルコールとは異なり、数がでないため客単価は低くなってしまいます。
回転率の悪さ
たとえ客単価が低くても回転率が高ければ売上を見込めますが、カフェは「飲み物を楽しみながらゆっくりと時を過ごす場所」というイメージが強い業態です。当然、長い時間滞在する顧客が多いため、回転率の悪さは否めず、客単価の低さと相まって売上は頭打ちになってしまいます。
物件選びの難しさ
低単価滞在型のカフェ業態では、ある程度の店舗面積が求められます。できるだけ席数を多くとって、席を埋めなければ利益が出ません。しかし、借りる物件が大きくなればその分、家賃は高くなります。その上、人手が必要になるため人件費も膨らむことになります。
また、郊外立地のカフェであれば駐車場の確保が必須です。カフェは一人来店も多いため、席数に対して十分な広さの駐車場がなければ席を埋めることができません。車での来店がメインの場合、駐車台数の理想は総席数の半分、最低でも総テーブル数以上が必要と言われています。
これらの条件をバランス良く満たし、かつ賃料が安い物件に出会えなければカフェ経営は難しいと言えるでしょう。
夜の集客の難しさ
18時以降のカフェのニーズは高くありません。夜に関しては、いくらフードメニューが充実しているとしてもレストランや居酒屋などには集客力で及びません。カフェの多くが夜の営業をしないのは集客が見込めないためとも言われています。
また、カフェバーのようなスタイルであれば夜の集客も見込めますが、営業時間が長くなるため、個人経営の場合、精神面、体力面が余程タフでなければ続けることは難しいと言えるでしょう。
競合の多さ
競合の多さもカフェ経営の難しさの一つです。競合は同じ規模感のカフェだけではありません。コーヒーが飲めるお店として、多店舗展開している大手カフェチェーン、ファミリーレストラン、ファストフード店をはじめ、パン屋やケーキ屋のイートインコーナーなど無数の競合が存在します。コンビニエンスストアのテイクアウトコーヒーも品質が高く、安価なため決して侮れません。
多くの競合の中から自店を選択してもらうためには、競合にはない価値を生み出すことが求められます。
これらの理由からカフェ経営がいかに難しいかが分かると思います。
長く続いている小規模のカフェが、必ずしも儲かっているとは限りません。それは、本業が別にある、他に収入がある、リタイアした方が趣味でやっている、自己所有の物件で賃貸料がかからないなどの理由があるケースが多いためです。
カフェ業態で利益を出し、長く続けていくことは他の飲食業態よりも過酷と言えるでしょう。周到な戦略がなければ安易にカフェの経営に乗り出すことは避けるべきです。
まとめ
今回はカフェ業態の特徴や経営の難しさなどについてお伝えしました。
カフェ経営は想像以上に厳しいものです。「カフェが好きだからやる」だけでは生き残れません。それでもカフェをやりたいという方は開業前に徹底的にカフェ経営のリスクを分析し、慎重に準備をすすめることをおすすめします。
後編ではカフェで成功するために求められることについて詳しくお伝えしますので是非続けてお読みください。