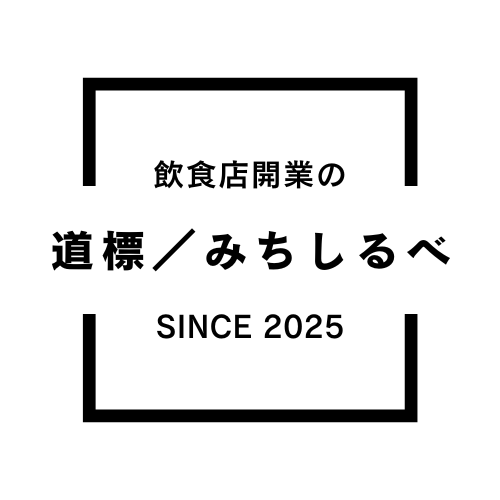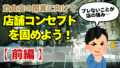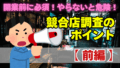前編では、飲食店になぜコンセプトが必要なのか?についてお伝えしました。コンセプト作りは開業に向けた第一歩として漠然としたイメージを可視化する非常に重要な取り組みです。後編では、コンセプトの作り方のポイントと作成後の活用方法について具体例を交えて解説していきますので是非最後までお読みください。
この記事は以下のような人におすすめ!
- 飲食店開業に向けて準備・検討している方
- 飲食店開業に向けてお店の特徴を決めかねている方
- 飲食店開業に向けてターゲットを決めかねている方
店舗コンセプトの作り方
コンセプト作りは、開業準備において最初の一歩といえる非常に重要なステップです。計画が準備の途中でブレないようにお店の軸となるコンセプトをビジネスシーンでよく使われる「5W2H」という手法に基づきまとめていきましょう。
5W2Hとは「why(なぜ)」「who(誰に)」「what(何を)」「when(いつ)」「where(どこで)」「how(どのように)」「how much(いくらで)」の頭文字からとられたものです。これら7つの要素をそれぞれ埋めて考えを可視化することで、なんとなく思い描いているお店のイメージを具体的に考えられるようになり、コンセプトの方向性を固めやすくなります。
作り方のポイント
- カギになるのは「who(誰に)」でターゲット層を誰に設定するかです。ターゲットが明確にならなければ、お店のイメージ、メニュー、サービス、立地などが定まりません。
- ターゲット層を「ヘルシー志向の方」や「育児中の女性」などに絞り込んだ場合、顧客満足度は高くなりますが、そもそも対象となる絶対数が少なくなるため、マーケット(市場)サイズが大きくない地方ではおすすめできません。
飲食店開業の5W2H
| why(なぜ) | お店を始める主な理由は? |
| who(誰に) | 顧客として見込むターゲットの年齢層、性別、職業は? |
| what(何を) | メニュー、味、量の特徴は? |
| when(いつ) | いつ開業するのか?営業時間は?定休日は? |
| where(どこで) | お店の場所はどこか? |
| how(どのように) | どんなふうに提供するか?どんな空間で提供するか? |
| how much(いくらで) | 客単価はいくらに設定するか?競合店と比べて高いか?安いか? |
具体例は以下の通りです。各項目を出来るだけシンプルにまとめることを意識しましょう。あれもこれもと内容を欲張り過ぎると全体がぼやけて「どんなお店にするのか?」を明確にするというコンセプト作りの目的から外れてしまいます。
具体例…居酒屋
| why(なぜ) | 仕事終わりのビジネスマンに栄養満点の料理を提供したい |
| who(誰に) | 30代~40代のビジネスマン・OL |
| what(何を) | ・肉、魚を中心としたボリューム感のある創作料理 ・彩り豊かな新鮮野菜を添えた食欲を掻き立てる盛り付け ・満足度の高い濃い目の味付け |
| when(いつ) | 令和〇年〇月開業予定、17時~24時営業、定休日:日曜日 |
| where(どこで) | A駅周辺、徒歩10分圏内の物件 |
| how(どのように) | ・お客様のペースに合わせた無駄がなくスピード感のある接客 ・居心地がよく、落ち着いた清潔感のある店内 |
| how much(いくらで) | 客単価4,500円、近隣の競合店の平均(4,000円)よりも高め |
具体例…ラーメン店
| why(なぜ) | 食べ盛りの若者にボリューム満点のおいしいラーメンを提供したい |
| who(誰に) | 10代~20代の学生、20代のビジネスマン |
| what(何を) | ・豚骨醤油ベースで太いストレート麺が特徴の家系ラーメン ・週に何度でも食べたくなるような飽きのこない味付け ・盛り付けには野菜をふんだんに使い、ボリュームも満点 |
| when(いつ) | 令和〇年〇月開業予定、11時~14時/17時~22時営業、定休日:日曜日 |
| where(どこで) | 〇〇大学、〇〇専門学校から徒歩10分圏内の物件、駐車場8台程度 |
| how(どのように) | ・様々なトッピングで自分好みにカスタマイズを楽しめる ・カウンター席を多く設け、一人でも気軽に来店できる ・券売機を導入し、オペレーションを簡略化する |
| how much(いくらで) | 客単価900円、近隣に同業態はなく既存の定食屋の客単価は850円 |
全てを記入することができればお店のイメージが少し具体的になってくるかと思います。そのうえで以下のポイントなどについてチェックしていきましょう。
- 全体的に整合性がとれているのか?
- ターゲット層の来店は見込めるか?
- ニーズがあるお店になっているか?
- 運営に無理はないのか?
- 売上を確保できるか?
これらを何度も見直して理想の店舗コンセプトを作りあげていきましょう。また、内容が自分だけの思い込みに偏っていないかを第三者(できればターゲット層に近い方)の目線でチェックしてもらうことも重要です。
店舗コンセプトの活かし方
出来上がったコンセプトは開業に必要な準備に活用することができます。以下のような内容に効果的に活用していきましょう。
店名の決定
コンセプトのイメージに基づいて店名を決めます。顧客が店名を見て興味を持ってもらえるよう、お店の雰囲気や魅力が伝わる名前を付けることが大切です。店名はお店のイメージを大きく左右するものなので、慎重に決めるようにしましょう。また、一目で何を提供するお店かがわかるよう以下のように店名の前後に肩書となるショルダーネームを付けることをおすすめします。
例)和風創作料理〇〇〇〇、鳥料理と地酒〇〇〇〇、珈琲専門店〇〇〇〇
メニューの作成
コンセプトに基づいてメニュー構成を検討し、味付けや盛り付けなどに反映させます。季節メニューやコースメニューを検討することで、さらに強いお店の独自性を打ち出せます。
例)地元食材にこだわる店では、その時期に最も旬の食材を使ったメニューを提供する。
テーマの統一
内装やサービスのスタイルも、コンセプトに合わせて設計することが大切です。メニュー、スタッフの制服、インテリアなどが統一されたテーマでまとめられていると、顧客に一貫した体験を提供できます。
例)和食レストランでは、落ち着いた和風のインテリアや伝統的な器を使用して、雰囲気と料理に一体感をだす。
ブランドイメージの確立
コンセプトを通じてブランドのイメージを確立し、顧客に強く印象付けます。店舗のロゴ、メニュー、ウェブサイトなど、視覚的な要素をコンセプトに合わせてデザインすることで、ブランドの統一感を保ち、顧客の記憶に残る店作りが可能です。
例)カジュアルなカフェでは、ポップで親しみやすいロゴやデザインを使用して、看板やメニュー表を作成し、カジュアルなイメージをアピールする。
スタッフの教育
スタッフに対してもコンセプトをしっかりと共有し、その理念に基づいたサービスを提供できるように教育していきましょう。スタッフがコンセプトを理解していると、より一貫した接客が可能になります。
例)家族向けの洋食屋では、子供へのフレンドリーな対応や家族向けサービスに重点を置く。
マーケティング戦略(販売促進活動)
コンセプトを基に、お店のマーケティング戦略を立てます。店の雰囲気や料理のテーマを反映させた広告やプロモーションを行うことで、ターゲット層に響くメッセージを届けられます。
例)ヘルシー志向のカフェであれば、SNSで健康的な食事やオーガニック食材を強調した投稿を行う。
リピーターの獲得
コンセプトを活かして、一貫したサービスや料理を提供することで、顧客は店に対して信頼感を持ち、再来店する動機になります。特にコンセプトが明確で、他店にはない体験を提供できる店は、リピーターを獲得しやすくなります。
例)ボリューム満点の定食を提供する店では、食欲旺盛な若者が定期的に訪れるようになる。
作り上げた店舗コンセプトを活用し、顧客に「うちはこういうお店です」という強い印象を残せるお店にできるように開業の準備を進めていきましょう。
まとめ
今回は前編・後編にわたって店舗コンセプトについてお伝えしました。飲食店の開業においてコンセプトがいかに重要で、どのように作り、活用すれば良いのかが伝われば幸いです。
私の経験上、コンセプト作りで最も怖いのは自分の思い込みです。開業の準備段階では多くの方が理想のお店作りに向けて集中しており、第三者からの意見が耳に入りづらい傾向にあります。そのため視野をこれまで以上に広げてコンセプトが本当にニーズを捉えたものになっているのかを冷静に判断することが必要です。
明確で整合性のとれた店舗コンセプトを作り上げることで、お店の魅力は顧客へと伝わり、来店動機につながります。日頃から「なぜこのお店は繁盛しているのか?」という目線を持ち続けることで数多くのヒントを得ることができ、コンセプト作りに活かせる筈です。浮かんだアイデアを活かして独自のコンセプトを作り上げて、着実に開業の準備を進めていきましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。