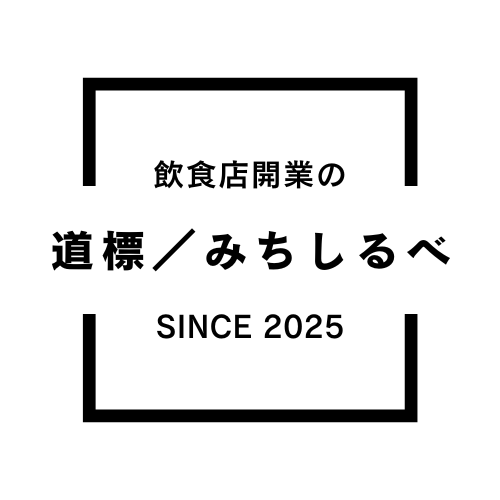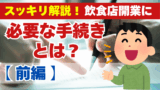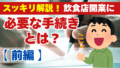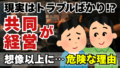前編では、飲食店の開業に必要な届出や手続きに関する情報と保健所への届出についてお伝えしました。
後編では、税務署や消防署などへの届出や手続きについて具体的に解説していきますので是非最後までお読みください。
本記事で紹介する情報は2025年7月時点のものです。最新の情報は届出や手続きを行う機関にてご確認ください。
この記事は以下のような人におすすめ!
- 飲食店開業に向けて準備・検討している方
- 飲食店開業にどのような手続きが必要か分からない方
- 飲食店開業に向けてどこで手続きすればいいのか分からない方
税務署への届出
個人事業の開業・廃業等届出書
飲食店を開業する際は、「個人事業の開業・廃業等届出書(以下:開業届)」を税務署へ提出する必要があります。開業届を提出する時期は開業してから1ヶ月以内と決まっているため、忘れずに提出しましょう。届出しなくても罰則はありませんが、後述の青色申告承認申請をするためには開業届を提出していることが前提となるため提出しておいた方が無難です。なお、届出をすることには以下のようなメリットがあります。
・屋号が付いた預金口座を開設できる
金融機関で新たに預金口座を作る際に、屋号を記載した開業届を持参すれば名義を「屋号+自分の氏名」にすることができます。具体的な手続きやルールは金融機関によって異なりますが、一般的には開業届を出した後でなければ、屋号での口座は開設できません。事業用の預金口座を作り、プライベート用と仕事用で使い分けることでお金の流れを管理しやすくなります。
・個人事業主であることの証明になる
個人事業主を対象とした支援制度を利用する際に開業届が必要になるケースがあります。たとえば、退職金の代わりとして共済金の積立ができ、節税対策にもなる小規模企業共済を利用する際には、個人事業主であることを証明するために開業届の控えが必要です。
開業届を出す際の注意点は以下の通りです。
・失業手当が受けられなくなる
会社員として雇用保険に加入していた人が退職した場合、再就職を希望するなら失業手当を受け取れますが、開業届を提出すると再就職する意思がないとみなされ、失業手当の受給資格がなくなるため注意が必要です。
・社会保険の扶養から外れる
配偶者の扶養に入っている人が開業届を提出すると、社会保険の扶養を外れなければなりません。大半の健康保険組合では、個人事業主は扶養の対象外となっているため、自ら社会保険料を負担する必要があります。
所得税の青色申告承認申請書
確定申告を青色申告でしたい場合には所得税の「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。確定申告のタイミングで提出しても青色申告はできないため、開業届と同時に提出することをおすすめします。提出する期限は申告する年の3月15日までです。また、その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出すれば、その年に青色申告ができます。
確定申告には、青色申告と白色申告があります。どちらを選ぶかは自由ですが、青色申告の場合、以下のようなメリットがあります。
- 最大で65万円の青色申告特別控除を受けることができる。
- 最長3年の赤字を繰越して翌年以降に黒字化して所得が発生した場合に、その金額から損失分を差し引くことができる。(個人事業主の場合)
- 家族従業員に支払った給与を経費計上できる。(青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要)
白色申告は日々の記帳が青色申告に比べて簡単ですが、上記のようなメリットが一切受けられないため、節税効果が高い青色申告がおすすめです。
給与支払事務所等の開設届
従業員(パートアルバイトを含む)を雇用する場合には税務署へ「給与支払事務所等の開設届」を提出する必要があります。従業員を雇用する事業主には源泉徴収義務があるため、従業員の給与から1年分の所得税を差し引き、本人(従業員)の代わりに納付しなければなりません。一人でも従業員を雇用する場合は開業届と同時に提出しましょう。提出すれば税務署から納付書や年末調整関係の書類が届くようになります。届出の期限は、従業員を雇用する事業所の開設日から1ヶ月以内です。
源泉徴収とは、給与や報酬を支払う事業主(会社)が給与の支払い時に、所得税などを差し引いて国などに納付する制度のことです。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉徴収分の所得税は、給与を支払った翌月の10日までに税務署へ納付するのが原則となっていますが、常時雇用する従業員(パート・アルバイトを含む)が10人未満の場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、納付を年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめてできるようになります。手続きの負担を大幅に軽減することができるため、常時雇用する従業員が10人未満であれば、開業届と同時に提出しましょう。届出の期限は特に定められていませんが、納期の特例は届出後に適用となります。
青色事業専従者給与に関する届出書
個人事業主が青色申告を行う場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出すれば、事業を手伝う家族従業員(青色事業専従者)の給与を必要経費に算入できるようになります。以下の要件を満たす家族従業員がいる場合は、開業届と同時に提出しましょう。届出の期限は家族従業員の給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、また、その年の1月16日以降開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2ヵ月以内に提出する必要があります。
青色事業専従者の主な要件
- 配偶者や親族であること:青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- 事業専従であること:その年を通じて6ヵ月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
- 年齢要件:その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
消防署への届出
消防署への届出は、提出が必須となるもの、条件次第で提出が必要となるものがあります。判断が難しいケースもあるため、できるだけ早い時期に管轄の消防署へ相談するようにしましょう。
防火対象物使用開始届
物件の工事の有無にかかわらず、飲食店を開業することを目的として建物や建物の一部を新たに使用する場合は、消防署へ「防火対象物使用開始届出書」を提出する必要があります。この届出は、消防署が管轄地域の飲食店の消防設備について正確に把握するためのもので消防法に基づき、火災予防の観点から提出が義務付けられています。提出期限は、建物の使用を開始する7日前までです。
防火対象物工事等計画届出書
開業の準備段階で対象物件において一定以上の工事や改修を行う場合は、消防署へ「防火対象物工事等計画届出書」を提出する必要があります。この届出は消防法に基づき必要とされ、火災予防のための措置が適切に講じられているかを確認することを目的として提出が義務付けられています。提出期限は、工事を開始する7日前までです。
火を使用する設備等の設置届
調理などで火を使用する設備を導入する場合は、消防署へ「火を使用する設備等の設置届」を提出する必要があります。この届出は、消防法に基づき必要とされ、火災リスクを最小限に抑えることを目的として提出が義務付けられています。提出期限は「設置を行う日の5日前まで」「設置工事開始の7日前まで」など、自治体ごとに異なるため管轄の消防署で事前に確認しておきましょう。
防火管理者選任届
従業員を含む収容人数が30人以上となる店舗の場合は、消防署へ「防火管理者選任届」の提出する必要があります。この届出は、消防法に基づき必要とされ、火災予防の体制を整えるため提出が義務付けられています。提出期限は営業開始日までです。また、防火管理者の資格を取得するには、防火管理講習の受講が別途必要です。講習の具体的な日時、会場、申込方法などは地域によって異なるため管轄の消防署で事前に確認しておきましょう。
警察署への届出
深夜酒類提供飲食店営業開始届書
夜12時から翌朝6時までの時間にアルコールを提供する場合は、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届書」を提出する必要があります。深夜における酒類提供飲食店の営業禁止地域もあるため、事前に確認しておきましょう。提出期限は営業開始日の10日前までです。届出をせずに営業すると50万円以下の罰金を科される恐れがあります。
労働基準監督署への届出
労災保険の加入手続き
「労災保険」は、従業員が勤務中や通勤中に労働災害にあった場合に補償を受けられる制度です。従業員を雇う場合、雇用形態(パート・アルバイトを含む)を問わず労働基準監督署で加入手続きが必要です。手続きは従業員を雇用した翌日から10日以内に行います。
ハローワークへの届出
雇用保険の加入手続き
「雇用保険」は、従業員が失業した場合に失業給付を受け取れる制度です。従業員の1週間の労働時間が20時間以上であり、31日以上継続して雇用する場合はハローワークで加入手続きが必要です。手続きは従業員を雇用した翌日から10日以内に行います。
まとめ
今回は前編・後編にわたって飲食店を開業する際の届出や手続きについてお伝えしました。飲食店の開業には多くの届出や手続きが必要なため、漏れのないように準備を進めていきましょう。
以前開業に関わった店舗ではオープン間近になって建物の構造上の問題で飲食店営業許可が下りず、大慌てで施工業者に頭を下げて突貫工事を行ったことがありました。なんとか保健所の許可が下りたのはオープンの前日という危うさでした。
オープン直前は様々な準備が重なるため、目が回る忙しさとなり、ミスが起こりやすくなります。届出や手続きの漏れが大きな失敗につながる可能性もあるため、チェックリストを作成し、一つ一つ着実にこなしていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。