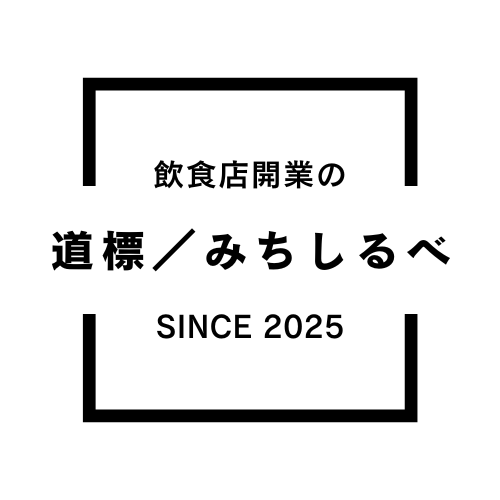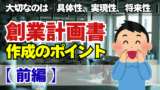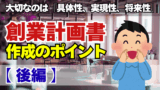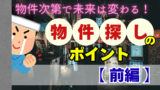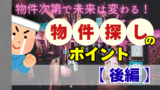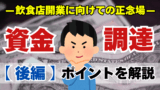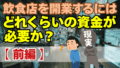飲食店を開業することは夢の実現に向けた第一歩ですが、成功を収めるためには入念な準備が欠かせません。準備は店舗コンセプト作り、創業計画書の作成、物件探しから資金調達まで考慮すべきポイントが多岐にわたります。本記事では、飲食店を開業する際に必要な準備と対策について詳しく解説しますので是非最後までお読みください。
この記事は以下のような人におすすめ!
- 飲食店開業に向けて準備・検討している方
- 飲食店開業に向けて何から手を付けたら良いかわからない方
- 飲食業界での経験値が不足していると感じている方
大半が準備不足…開業に向けて何から準備すべきか?
私の経験上、飲食店の廃業率が高いと言われる理由は、開業する多くのお店が明らかに準備不足のまま開業を迎えているケースが多いためだと考えています。
「勝負は開店してから!」という認識は大きな間違いです。開業後は仕入れや仕込みなど日々の業務に追われるため、思うように売上が上がらないからといって営業を続けながらお店のコンセプトを見直して軌道修正することは容易ではなく、手元資金が不足した状況では次なる一手を打つ余裕はありません。つまり、飲食店経営は開業を意識した時点からすでにスタートしていると言っても過言ではないということです。
開業準備には、店の規模や業態、立地条件などによって異なるものの1年程度の期間を設けることをおすすめします。オープンまでにやるべきことは山積みです。それらの準備が不十分だと、開業しても早々に廃業に至る可能性が高くなります。何から手を付けたら良いのかわからない方は以下のステップから準備をスタートしてください。
各項目は内容がそれぞれ多岐にわたるため詳細は別の記事で詳しくお伝えします。
店舗コンセプト作り
まずは店舗コンセプトを固めていく作業からスタートします。計画が準備の途中でブレないようにお店の軸となる基本コンセプトをビジネスシーンでよく使われる「5W2H」という手法に基づきまとめていきます。5W2Hとは「why(なぜ)」「who(誰に)」「what(何を)」「when(いつ)」「where(どこで)」「how(どのように)」「how much(いくらで)」の頭文字からとられたものです。これら7つの要素をそれぞれ埋めていくことで店舗コンセプトを具体化することができます。
なお、店舗コンセプト作りは、出店エリア、競合店を想定しておく必要があります。競合店調査と並行して取り組みましょう。
| why(なぜ) | お店を始める主な理由は? |
| who(誰に) | 顧客として見込むターゲットの年齢層、性別、職業は? |
| what(何を) | メニュー、味、量の特徴は? |
| when(いつ) | いつ開業するのか?営業時間は?定休日は? |
| where(どこで) | お店の場所はどこか? |
| how(どのように) | どんなふうに提供するか?どんな空間で提供するか? |
| how much(いくらで) | 客単価はいくらに設定するか?競合店と比べて高いか?安いか? |
創業計画書作成
創業計画書は固まった店舗コンセプトを具体的な計画に落とし込む書類になります。お店のセールスポイントやターゲットとする客層などに加え、資金計画や収支計画などを具体的に記載します。
- 金融機関(銀行、信用金庫、日本政策金融公庫など)からの資金調達が必要な場合、創業計画書を作成し、提出することが必須となります。
- 創業計画書の様式は金融機関ごとに異なりますが基本的な記載内容は大きく変わりません。店舗コンセプトをしっかり固めていれば、その内容を転用できるため作成が容易になります。
- 創業計画書には開業前に必要な資金(物件取得費用、内外装工事費用、設備導入費用など)の総額がどれくらい必要で、その資金をどのように調達するかを示す「資金計画」が含まれています。その内容は次項の「物件探し」で重要な役割を果たします。
物件探し
物件探しは開業の成功のカギを握る重要なポイントです。ターゲットとする客層が訪れやすい場所であるか、コンセプトを実現できる店舗スペックであるか、競合店の存在、家賃などのバランスを考慮して慎重に選定しましょう。気になる物件は積極的に管理している不動産会社などへ問い合わせ、しっかりと内見し、物件の状態を確認しましょう。希望の条件を全て満たす理想の物件と出会えることはなかなかありません。そのため絶対に譲れないポイント、妥協しても良いポイントを予め想定しておくことが必要です。借りたい物件が決まったら施工業者(工務店など)へ諸条件を伝えて見積書を作ってもらいましょう。以下は物件を選定する際に抑えておきたいポイントの一例です。
- 視認性、入りやすさ
- お店前の人通り
- 近隣の人口や属性(年齢層・職業・性別など)
- 家賃
- 面積(ホール・キッチンの広さ)
- 内外装の状態
- 設備の状態(厨房機器・ダクト・グリストラップ・エアコン・トイレなど)
- 駐車場(郊外立地の場合)など
資金調達
自己資金、金融機関からの融資、助成金などの選択肢を検討し、開業に必要な資金を調達します。創業計画書を軸に資金の使い道をしっかりと見積もりましょう。
- 店舗(物件)は融資を申し込むまでに決めておく必要があります。仮押さえの状態でも問題はありませんが物件取得(保証金[敷金]、礼金、仲介手数料、前家賃など)、内外装工事、設備購入にかかる費用の見積書が必要になります。
- 開業時の融資における資金使途は物件取得費、内外装工事費、設備導入費などの「設備資金」が一般的です。「設備資金」は仕入れ、家賃、人件費などの「運転資金」に比べ、返済期間を長期で組むことができ、月々の返済額を抑えられるメリットがあります。
取り組む順番に厳密なルールはありませんが、①店舗コンセプト作り、②創業計画書作成、③物件探し、④資金調達の流れで進めるのが一般的です。
また、開業において先に物件を押さえてから準備を開始する手法はおすすめできません。店舗コンセプトや創業計画書の作成、必要な工事など諸々がその物件ありきで進めることになるため、必然的に難易度が高くなります。結果的に家賃を多く支払わなければならないことも多いため、大切な開業資金を減らしてしまうことにもつながります。
創業計画書は、開業後もお店の目標や方向性を指し示してくれる重要なアイテムになります。長くお店を続けるためにも、着実に開業までのステップをこなしていきましょう。
こちらもおすすめ!
- 準備段階で時間が確保できる方は学びの場として商工会議所や商工会が定期的に開催している創業塾(起業塾や創業スクールなど名称は様々)などに参加することを検討しましょう。短期集中型の講座で経営に関する基礎知識を学べることに加え、同じく開業を志す方々と出会うことができ、新たな人脈を築くことにもつながります。
- ネット上のYouTubeなどでは飲食店経営に関する有益な情報がたくさん公開されています。スキマ時間に情報収集することを習慣づけましょう。
準備を進める段階で飲食店経営の大変さを痛感することもあると思います。常に不安と隣り合わせの状態で計画を推し進めていくためには心の余裕と相当のエネルギーが必要です。検討した結果、開業を断念もしくは延期することも選択肢の一つだという事を忘れないようにしてください。
まとめ
今回は飲食店の開業に向けて何から準備すればよいのか?についてお伝えしました。
飲食店経営に「絶対こうすればうまくいく」という答えはありませんが準備を重ねるほど成功の可能性を高めることはできます。また、繁盛しているお店には必ずなんらかの成功要因があります。そして、たくさんのお店の中から選ばれ、来店してもらうためには明確な他店との違い(差別化)が必要です。そのためお店のコンセプトをしっかりと固め、ブレない創業計画を作り上げていく作業は欠かせません。飲食店開業という夢を実現するため着実に作り上げていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。